退職するに際し、ライフプラン(キャッシュフロー)を策定する中で貰える年金額がどの程度となるか調べたところ、加給年金と振替加算という用語が出てきました。自分なりに調べて年金額に加給年金分を加えて計算しました。加給年金について、既に承知されている方も多いと思いますが、当方の知識の再確認の意味合いも含め、以下のとおり整理してみました(日本年金機構のHPを引用)。みなさんの参考となれば幸いです。当方の理解誤り等あればご指摘ください。
加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金のことです。加給年金は、会社員や公務員といった厚生年金の受給者が対象であり、自営業などで国民年金を受給する人は、配偶者や子どもなどの扶養家族がいても対象とはなりません。
なお、加給年金は配偶者が64歳未満であること等年齢制限があり、年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
加給年金の額は、配偶者と1人目・2人目の子については各234,800円で、3人目以降の子は各78,300円となっており、また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方(受給権者)の生年月日に応じて、34,700円から173,300円が特別加算されます。詳細については、添付ファイルの「加給年金額と振替加算」を確認いただきたいのですが、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後であれば、加給年金額の合計は408,100円となります。
なお、加給年金額加算のためには、届出が必要となるほか、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。また、繰下げ待機期間(年⾦を受け取っていない期間)中は、加給年⾦額や振替加算を受け取ることが出来ないことは十分留意する必要があります。
加給年金に関連し、振替加算制度がありますが、当制度については次回ご報告させて頂きます。
年金制度については、理解が難しい面がありますので、日本年金機構のHPをご覧いただくほか、必要に応じてねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所に照会されるのが良いと思われます。
当方はFPの資格試験勉強において、年金も勉強しましたがすっかり忘れております。自分の老後にも関係するので再度しっかり勉強し、成果は皆さんにご披露できればと思っております。
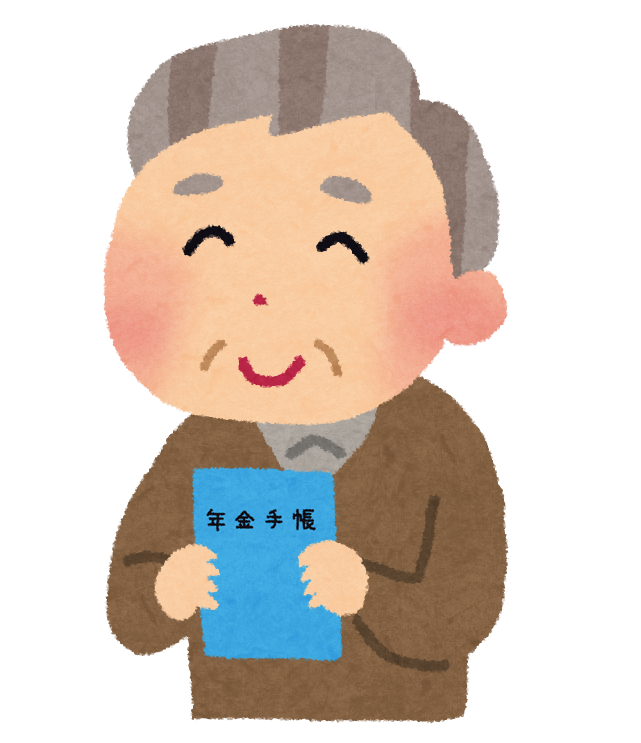
コメント